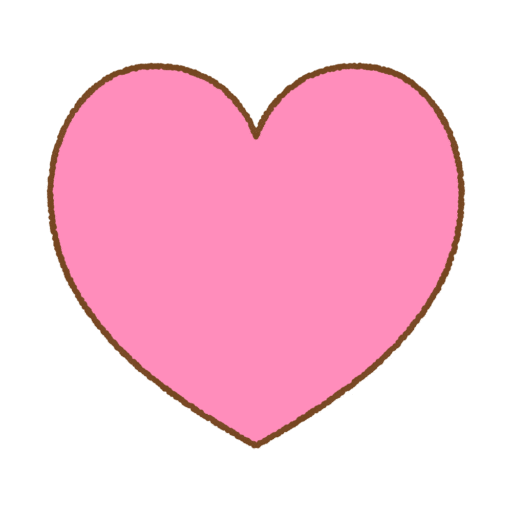このページにはプロモーションを含みます。
「夜に災害が起きたその時、あなたはすぐに灯りを手にできますか?」
突然の地震。鳴り響く警報、揺れる大地、そして……停電。夜であれば、視界は一瞬で真っ暗になります。都市でも、家の中でも、頼れるのは備えていた“光”と“電源”だけです。
こんにちは、キャンプ歴15年の防災マニアです。キャンプという非日常を楽しむための装備や知識は、実は“非常時”にもそのまま活かせるものがたくさんあります。
被災後すぐに求められるのは、水や食料といった生命維持に関わるものに加えて、「情報を得る手段」や「灯り」、つまり“電源”の確保です。これらがなければ、暗闇の中で不安な一夜を過ごし、家族や大切な人の安否も分からず、孤立する恐れすらあるのです。
私がキャンプを通じて身につけた「電源との付き合い方」は、日常でも非常時でも変わりません。今回は、「被災初期」から「自宅避難の長期化」までの2つのフェーズに分けて、電源確保のポイントを詳しくお伝えしていきます。
あなたの大切な人を守る備え、今日から始めてみませんか?
もくじ
- 被災直後に必要な「電源」確保術
- 懐中電灯と乾電池の正しい選び方
- 情報は命を守るツール──携帯ラジオの重要性
- スマホは命綱:モバイルバッテリーとケーブルの備え
- 長期化する自宅避難での電源確保
- 「復旧までの時間」は想像以上に長い
- ポータブル電源が支える“被災生活”
- ソーラーパネルとの併用で「完全自立型」へ
- 災害が起きなくても「備え」が快適さに変わる
- まとめ
被災直後に必要な「電源」確保術
■ 懐中電灯と乾電池の正しい選び方
夜間の被災直後、一番最初に必要なのは“灯り”です。懐中電灯やヘッドライトがあるだけで、視界が確保され安全な行動ができます。ここで重要なのが「乾電池の統一」です。
私はキャンプ用装備もすべて、単3電池で統一しています。こうすることで、予備の電池が1種類で済むため、管理が格段にラクになります。
たとえば、単3電池を使うLED懐中電灯と、同じく単3で動く携帯ラジオを選んでおけば、乾電池が切れたときもすぐに入れ替えができます。サイズが統一されているということは、それだけで“安心”に直結するんですね。

■ 情報は命を守るツール──携帯ラジオの重要性
今の時代、情報収集のメインはスマートフォンでしょう。しかし、地震の直後には通信障害が起きたり、基地局の電源が落ちて繋がらなくなることも。そんなとき、アナログな携帯ラジオが最強の味方になります。
しかも最近はLEDライトや手回し発電機能が付いた多機能ラジオもあります。これも単3電池も使えるものを選ぶのがコツです。
■ スマホは命綱:モバイルバッテリーとケーブルの備え
スマホは情報収集だけでなく、家族との連絡、安否確認、カメラ、メモ、懐中電灯の代用など、まさに多機能な“情報の命綱”です。だからこそ、モバイルバッテリーの備えは欠かせません。
私のおすすめは、「10,000mAh以上」「2台同時充電が可能」「充電残量のインジケーターがある」タイプ。アウトドアや災害時でも、残量を可視化できる安心感は絶大です。
もちろん、充電用ケーブルも忘れずに。スマホとモバイルバッテリーで端子が違う場合は、両方の規格(USB-C、Lightningなど)に対応するアダプターをポーチに一緒に入れておきましょう。

真っ暗な中、いざ懐中電灯やバッテリーを探すのは難しい。だから私は、就寝時に“災害用ポーチ”をベッド脇に必ず置いています。中身は以下の通りです。
- 懐中電灯(ヘッドライト)
- 携帯ラジオ
- モバイルバッテリー
- スマホ充電ケーブル
- ホイッスル
このホイッスル、意外に思うかもしれませんが、瓦礫に閉じ込められたとき、自分の位置を知らせる最後の手段になります。実際、阪神淡路大震災ではこのホイッスルが救助の決め手になった事例もありました。
これらを防水性のあるポーチにひとまとめにしておくと、夜中に災害が起きたときでも慌てず対応できます。
長期化する自宅避難での電源確保
■ 「復旧までの時間」は想像以上に長い
東日本大震災では、被災地域の停電が完全に復旧するまでに最大で1ヶ月以上を要したエリアもありました。熊本地震では、避難所や自宅での停電状態が10日以上続いた家庭も多く、スマホの充電や冷蔵庫の使用、電気ポットの使用ができないことで生活の質が大きく低下しました。
つまり、「自宅避難=電源がある」という前提は成り立たないのです。ならば、どうやって電源を確保するか?
ここでアウトドア経験者が信頼を寄せるアイテムが「ポータブル電源」です。
■ ポータブル電源が支える“被災生活”
ポータブル電源とは、コンセントのない場所でも家庭用の電気製品が使える充電式のバッテリーです。スマホはもちろん、扇風機、電気毛布、小型冷蔵庫、炊飯器といった家電も動かせるモデルもあります。
私が愛用しているのは【pecron】のポータブル電源シリーズ(https://www.pecron.jp/)。中でも「E1500LFP」は、キャンプでも災害時でも信頼できるスペックを誇ります。
スペック
- 定格出力:2200W
- 容量:1536Wh
- 出力ポート:AC100V×3、USB-C×2、USB-A×4、シガーソケット×1
- 重量:約18kg
- 安全性の高いリン酸鉄リチウム電池
ポータブル電源としては小さいほうながら、スマホを約90回、ノートパソコンを約20回、LEDランタンであれば数日間連続点灯できるレベルの実力です。

■ ソーラーパネルとの併用で「完全自立型」へ
さらに安心なのは、同じくpecron社の「ソーラーパネル(SP100)」と組み合わせること。日中にソーラーパネルで充電→夜に使用、というサイクルを組めば、電気の“自給自足”が実現します。
天気に左右される点はありますが、長期避難が現実となったとき、この装備はまさに“情報の命綱”になることでしょう。
■ 災害が起きなくても「備え」が快適さに変わる
ポータブル電源やソーラーパネルは、災害時だけでなくキャンプや車中泊でも大活躍します。夏なら扇風機、冬なら電気毛布。コーヒーメーカーや炊飯器を使えば、アウトドアでも“家庭のような快適さ”が手に入ります。
「備えは不安のためじゃない、安心のためにある」──そう思えるのも、この装備のおかげです。
まとめ
災害時、自宅避難の際の「電源確保」は、水や食料と同じくらい大切です。
突然の停電、途絶える通信、闇に包まれる夜……。でも、たったひとつの懐中電灯、予備の電池、充電済みのモバイルバッテリーがあれば、その一夜を安心して乗り越えられるかもしれません。
さらに、自宅避難が長期化すれば、“電気をどう確保するか”が生活の質を大きく左右します。ポータブル電源とソーラーパネルの組み合わせは、電気のない世界でも“希望の光”となってくれるでしょう。
そして何より、それはキャンプや車中泊という楽しい時間でも使えるものです。日常に寄り添う防災──これが、私の目指すスタイルです。
さあ、あなたは今日からどんな“電源の備え”を始めますか?